【業務委託で働く6つの注意点】扶養内在宅ワークをしている主婦が教えるリアルなデメリット
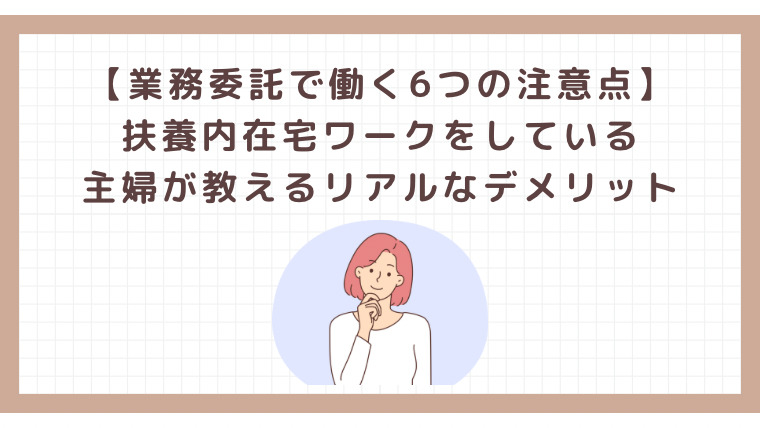
最近、よく見かける「業務委託」という働き方。
コロナ禍をキッカケに在宅勤務の需要が上がり、主婦向け在宅ワークの求人では「業務委託」での募集を目にする機会が増えました。
自由度高く、得意を活かして在宅でも稼げるというメリットがありますが、収入額によっては働き損となる場合があります。

フツーに時給で働ける会社も多いし、業務委託とパート、何が違うんだろ?

現在、業務委託契約を結んで仕事をしている私が、業務委託で働く注意点について紹介します。
まず、業務委託には2種類の契約があります。
- 請負契約 業務に対して成果物を完成させる責任を負う
- (準)委任契約 業務を行うことに対して報酬が支払われるが成果物を完成させる責任は負わない
軽い気持ちで業務委託契約を結ぶと、後々後悔やトラブルにつながるリスクがあります。
特に「配偶者の扶養の範囲内で働きたい方」は要注意です。
特徴をしっかり理解した上で契約しましょう。

リスクが大きいと判断した場合は契約前に断る勇気を。この契約書を交わした後は重く、しばられるものになります。
業務委託は労働法で守ってもらえない
求人上、一見普通のパートと条件は変わらないように見えますが、パートの場合は雇用契約・業務委託では業務委託契約になります。
この契約内容の違いによる業務委託の最大のリスクは「労働法の対象外」になることです。
- 労働法の対象外となるもの
- 雇用保険なし(失業手当受けられない)
- 労災保険なし(業務中の病気、ケガの際の給付なし)※特別加入制度はあり
- 社会保険なし(健康保険料・厚生年金保険料なし)
- 最低賃金法適用なし
- 労働時間のきまりなし
- 残業手当のルールなし
- 休憩・休日のきまりなし
- 労働安全衛生法適用なし(健康診断・メンタルチェックなど)
- 産前産後休業、育児休業、介護休業、それぞれなし
- 休業手当なし
- 年次有給休暇なし
参考:厚生労働省

厚生労働省のホームページ上でも、業務委託契約締結し、フリーランスとして働くことの注意喚起が行われています。
パート、アルバイト、契約社員、派遣社員であれば、企業と雇用関係があるため労働法で守られますが、業務委託契約を締結して働く立場になると、発注者の指揮命令を受けない「個人事業主/フリーランス」として扱われるため、労働法は対象外です。
労働法で守られないので、自分のことは自分で守るしかありません。
企業との雇用関係はないので、対等な立場になる点がポイントです。
自分を守るために、不服に思ったことは、遠慮せず、ハッキリ伝えましょう。
- 企業とは対等の立場になるため、割に合わない仕事は引き受けなくてOK(最低賃金法で守られないので注意)
- 【国民健康保険、国民年金に加入する】または【夫の社会保険扶養の130万円未満の範囲内で働く(注意3参照)】
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)や小規模企業共済掛金に加入して自ら退職金を準備する
- つみたてNISAなど投資で資金を増やす
- 地域の健康診断を利用する
個人事業主として開業は必要なのか?

業務委託契約したら、税務署に開業届出すのよね?

確認してからにしましょう!
業務委託契約の場合、企業とは雇用関係にないため年末調整などは対象外です。
そのため、自主的に、毎年1年分の所得(1~12月分)を計算した確定申告書を作成して、2/16日~3/15までに税務署に提出し、儲けがあれば所得税を納める必要があります。
その確定申告書を作成するための計算方法は、所得の種類によって違いがあり、業務委託であれば、一般的に事業所得または雑所得に該当します。
- 事業所得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいう(業務に係るものは雑所得になる)
引用:国税庁
- 雑所得 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいう【副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当】※一部抜粋
引用:国税庁
自身の業務内容が、どちらの所得に該当するかの判断は、個人事業主になるか否かの分かれ道になります。特に、旦那さんの扶養の範囲内で稼ぎたい場合は、軽い気持ちで開業してしまうと、後々後悔につながる可能性があるため、慎重な判断が必要です。
所得税法では、業務に係るものは雑所得になると定められていますが、この「業務」部分が具体的に何を指すかは、詳しく書かれていません。
税務署に電話で問い合わせてみました。以下、リアルなやり取りを記録します。
税務署の担当者一人目

事業所得の定義に、「業務に係るものは雑所得」とありますが、この業務は何を指しますか?

単発で完結するような業務を指します。反復、継続しない業務です。

業務委任契約で働いていますが、内容は、担当を持って継続して行うものではないです。毎日仕事があるわけでもないです。指示された業務を一つずつ、完結していく感じです。これは雑所得でよいですか?

業務委任契約を結んでいるなら、税務署としては反復・継続する業務と判断します。

夫の扶養の範囲内ほどの収入ですが、開業して個人事業主になるのですか?

金額の大きさではなく、業務内容で判断します。個人事業主でも、所得税上での扶養には入れますよ。

所得税の扶養には入れても、個人事業主になると、会社によっては社会保険上の扶養に入れなくなる可能性があるんです。
また、契約中の税理士からは、開業せず雑所得で申告してよいと言われました。どちらが正解なのですか?

繰り返しになりますが、税務署では業務委任契約を結んで反復・継続した仕事の場合は事業所得になるとしかいえないです。

例えば、業務委託のほかに給与収入があって、給与収入がメインで業務委託を副業とする場合は、業務委託は雑所得になりますか?

そういった場合でも、判断は変わりません。業務委任契約であれば、事業所得です。
念のため、税務署の担当者二人目にも相談

契約中の税理士からは、業務委任契約でも開業する必要はなく、雑所得で申告してよいと言われましたが、先日相談した税務署の方からは事業所得だと言われました。どちらが正しいのですか?

プロ(税理士)の判断に従ってください。

むむ、結局、よく分からないぞ?
結論!素人には判断できないため専門家に確認する
- 業務委任契約を交わす前に、自身の業務内容が事業所得・雑所得どちらの所得に該当するのか確認したほうがよい(顧問税理士に確認してもらう)
- 業務委任契約で、反復・継続した業務を行う場合は事業所得になり、個人事業主として開業し、確定申告が必要
- 単発で完結する業務の場合は雑所得に該当するため開業は不要(雑所得として確定申告が必要)
参考:国税庁 税務大学校論議

事業or非事業の判定は難しいんですね
夫の社会保険扶養を抜けなければならない可能性
個人事業主になっても、夫の扶養に入ることは可能です。
ただし所得税と社会保険の扶養では、条件が異なる点、注意が必要です。
以下、2種類の扶養条件を簡単にまとめました。
- 所得税上の扶養 年間所得合計額が48万円以下(配偶者控除対象)
- 年間所得合計額48万円超〜133万円以下(配偶者特別控除対象)
- 社会保険上の扶養 継続的な年間収入が130万円未満

所得税は配偶者特別控除もあるのでそこまで大きい負担にならずすむと思いますが、社会保険は、扶養を抜けると自己負担が大きいため、要注意です。
社会保険上の扶養の注意点(家族手当にも注意)
まず、扶養を抜けると影響が大きい、社会保険上の扶養についてご紹介します。
- 社会保険上の扶養 継続的な年間収入が130万円未満
個人事業主の年間収入130万円未満の考え方
収入(企業からもらう業務委託報酬)-直接的な必要経費(所得税で認められている必要経費ルールとは異なり厳しい)=130万円未満
※ひと月あたりの収入額108,333円
ひと月あたりの収入額を上回る収入が恒常的にあると認められる場合は認定されない

目安として130万円を超えないように稼げば、確実に社会保険の扶養に入れるかな?

その判断は旦那さんの会社によって異なります。
会社によっては、個人事業主になると、収入の金額に関わらず、社会保険の扶養から抜けなければならない可能性があります!
通常、夫が会社員の場合は、妻が130万円未満の収入であれば社会保険の扶養に入れます。扶養に入れば、妻の社会保険(健康保険・厚生年金)の負担額0というのは、大変ありがたいことです。
ところが、開業届を出して個人事業主になると、会社によっては、事業所得の多少にかかわらず、夫の扶養を抜けなければならない可能性があります。それだけに限らず、扶養手当(家族手当)まで支給対象外になる可能性があります。
この判断は、会社によるとしか言いようがないため、できれば業務委託契約を締結する前に、会社のホームページ福利厚生部分の部分を確認したり、旦那さんより健康保険組合等に「妻が個人事業主になっても扶養に入れるか」確認してもらった方がよいと思います。個人事業主でも扶養に入れるのであれば安心して開業できます。
万一、自身の収入額が130万円を超えないにも関わらず扶養を抜けなければらならない場合、自分で国民健康保険と国民年金に入り、毎月数万円の自己負担額を払っていかなければなりません。そのほか、家族手当も不支給になった場合は、かなりの痛手になります。
扶養の範囲内でしか稼げないのであれば、手取りが減り、働き損になるためご注意ください。
- 個人事業主になると、配偶者が務める会社の判断によっては、収入の多少関係なく、社会保険の扶養から抜けなければならない可能性と、家族手当の支給が対象外になってしまう可能性があるため注意
- 働き損とならないために、収入額アップを目指す
- 国民健康保険と国民年金を自己負担する場合、一般的に171万円以上から収入プラスになるといわれている
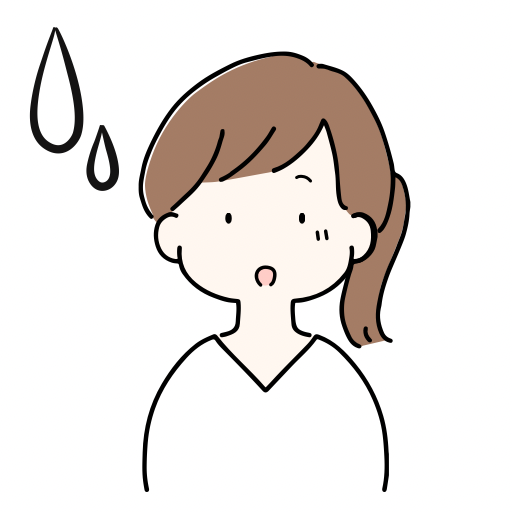
130万円未満の収入を考えていたのに、困ったな・・
毎月15万円ほど稼ぐのは、パートレベルの業務委託では厳しい

収入を増やすことが難しいなら、業務委託契約を結ぶ前に契約辞退する勇気も必要です。。
所得税上の扶養の注意点
次に、所得税上の扶養について紹介します。
- 所得税上の扶養 年間所得合計額が48万円以下(配偶者控除対象)
- 年間所得合計額48万円超〜133万円以下(配偶者特別控除対象)
給与所得でないため、よく言われる「103万円(配偶者控除)・150万円(配偶者特別控除)」の壁というものに該当しません。
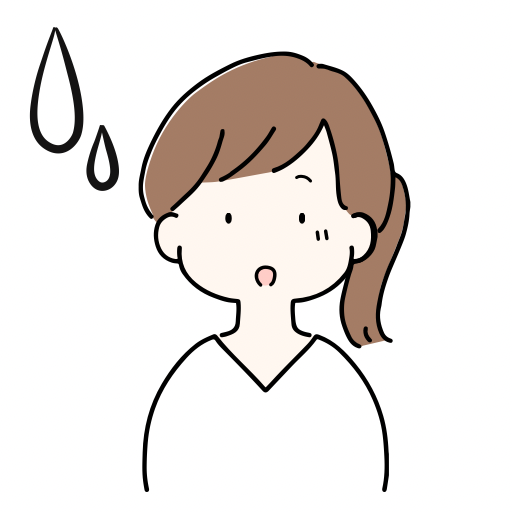
扶養の範囲内におさえたい場合、個人事業主になったら給与103万円以下じゃなくて、48万円以下まで収入をおさえなきゃいけないってこと?

48万円というのは収入でなく、所得のことです。ややこしいですよね。
業務委託で事業所得に該当する場合、計算式は以下の通りです。
事業所得の計算式
収入(企業からもらう業務委託報酬)- 必要経費 = 所得
この「所得」が48万円以下であれば扶養に入れる!
48万円というのはすべての人が引くことができる基礎控除額(変動あり)の金額。所得48万円-基礎控除額48万円=0円となるため扶養に入ることができる。
ポイントは、収入から引ける「必要経費」です。なんでもかんでも経費として落とせるのではなく、事業に必要な経費のみです。青色申告・白色申告の選択によっても必要経費の範囲が異なるため注意。参考まで、在宅ワークで私が経費としているものを紹介します。
- 業務用パソコン
- パソコンデスク
- 事務用品
- 書籍
- バーチャルオフィス利用料
- 会計ソフト使用料
家賃、水道光熱費なども、事業としての計算根拠を示せれば必要経費として計上可能。詳しくは税務署や税理士の相談窓口に確認がオススメ。

在宅ワークだと、大きく経費にできるものはないですね。
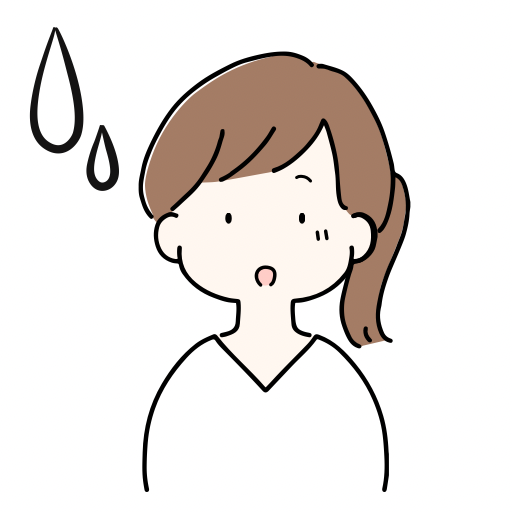
そうなると、とても48万円以下の所得にできないと思うけど・・

がんばって帳簿をつけて、青色申告すれば大丈夫ですよ!
- 白色申告 青色申告以外はこちら。特典はなし。
- 青色申告 必要な時期(人により異なる)に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出
- 帳簿の条件を満たした複式簿記で記帳し確定申告 55万円(青色申告特別控除額)
- 上の条件で、さらに電子申告または電子帳簿保存すれば控除額プラス10万円
- 帳簿の条件を満たした簡易簿記で記帳し確定申告 10万円(青色申告特別控除額)
- そのほか、赤字になったときの損失額を繰り越すことができたりと、青色申告の特典は豊富!
事業所得が48万円以下の場合、確定申告の必要はないが、敢えて申告したほうがよい場合もある
- 赤字の場合 青色申告なら赤字を繰り越せる
- 業務委託のほかに給与収入などがあり源泉徴収されている場合 源泉徴収で引かれた所得税が戻ってくる可能性あり
- 所得税とは別に住民税の申告が必要な場合あり所得税がかからなくても住民税がかかる場合があるため確定申告しておくと後々ラクな場合も(確定申告すれば税務署より市区町村に所得データが共有されるため)
在宅ワークの場合、収入から引ける経費はたかが知れているので、給与の扶養の範囲内と同じくらい働く場合、とても48万円以下の所得におさえられませんが、青色申告で確定申告すれば、最大65万円の青色申告特別控除を受けることが可能になり、収入から引くことができます。
ただ、青色申告で確定申告するためには「開業届」と「青色申告承認申請書」を、提出期限(事業開始日によって異なる)までに税務署に提出が必要です。
開業した年度分から青色申告したい場合の提出期限
- 開業届 原則、開業してから1ヶ月以内に提出
- 青色申告承認申請書 事業開始日から2か月以内(年度途中で開業した場合)
青色申告承認申請書は、忘れないように開業届と同時提出がオススメ!
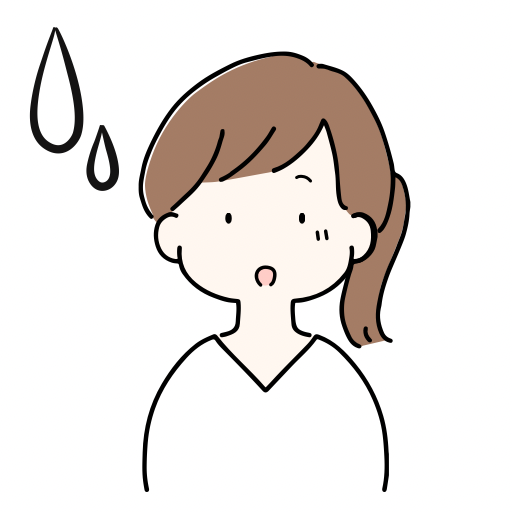
青色申告だと複式簿記で帳簿をつけなければならないのね。なんだか難しそう…
簿記分からないけど大丈夫かな?

今は、質問形式で答えていくだけで、複式簿記に対応した帳簿がつけられる会計ソフトのアプリがあるので、なんとかなりますよ!
小規模個人事業主向けのプランは負担のないお値段で利用できます。
個人事業を開業したら、1カ月以内に開業届を提出する必要があります。
freeeまたはマネーフォワードの会計ソフトを利用すれば、質問に答えていくだけで無料で作れるのでオススメです。
最低賃金法で守られないため働き損に注意
業務委託は労働法の一つ「最低賃金法」で守られないため、時給制でない契約の場合、知らぬうちに損をする働き方をさせられる可能性があります。

私の経験談を紹介します。
例:記帳代行の落とし穴
完全在宅ワークのお仕事でよくあるお仕事の一つに、記帳代行があります。
企業や個人の代わりに、通帳や領収書などの書類を基に、帳簿をつけるお仕事です。
在宅の場合、会計事務所や記帳代行会社の、外注先(内職のようなイメージ)として働くパターンが多いです。
私が契約した際の記帳代行単価は、1仕訳10円でした。

応募の時点では、深く考えていなかったのです。
1仕訳10円の重さを・・
以下、分かりやすく、業務内容の比較表でご説明します。
| 業務時間/3時間 | 通帳 (単純な転記入力) | 現金出納帳 (自分で判断し仕訳) |
|---|---|---|
| ①仕訳数 | 400仕訳 | 100仕訳 |
| ②仕訳数×10円 | 4,000円 | 1,000円 |
| ③時給換算(②÷3h) | 約1,300円 | 約300円 |
お分かりいただけましたでしょうか?
2023年10月現在、東京都の最低賃金は1,000円を超えています。
それにも関わらず、このような仕訳単価契約の場合、上記の比較表の現金出納帳の例のような仕事を引き受けると時給換算300円になります。
企業と業務委託の関係は対等な立場につき、このような仕事の依頼は断る選択も可能です。
しかし、記帳業務は、いざ蓋を開けてみないと、アタリ(稼げる)かハズレ(損する)か分かりません。
書類管理にルーズな会社や個人の記帳を請け負うと、経費にできないものや、クレジットカード払いのレシートや領収書が混ざっていることなんてしょっちゅうなので、確認作業には想像以上に時間がかかってしまいます。
ちなみに、記帳代行を依頼している会社や個人は、会計事務所や記帳代行業者に対して、1仕訳100円くらいを相場に記帳代行料金を支払っています。
それに対して、会計事務所や記帳代行業者は、お客様からもらう料金の10分の1相当の安い金額で、外注先に業務委託し、儲けているのです。
このような損をする働き方をしないためには、以下のポイントを参考に、細部まで契約内容を確認することをオススメします。
- 仕訳単価報酬制の場合
- 仕訳内容を考慮した単価変動はあるか?(一律価格の場合は損する可能性あり)
- 対象外の領収書等の確認作業も、1仕訳の報酬としてカウントされるか?
- 業務委託でも、時給制で働ける企業を選ぶ
仕事で使うものは自分で準備が必要になる場合がある
事務系完全在宅ワークの場合、業務委託求人でよく見かけるのが「自分で準備が必要なもの」の条件です。
直接雇用であれば、パソコンなど業務に必要な物は会社に準備してもらえますが、企業と業務委託という関係上、必要な物は「業務委託を受ける側」で準備しなければならない場合があります。
以下は、求人で見かけた一例です。
自分で準備が必要なものの条件例(企業による)
- パソコン(中~高スペック・webカメラ付き)
- 通信環境10~30Mbps以上
- 有料ウイルスソフト
- 有料のMicrosoft Office
自費で負担したものを業務で使用する場合、上記の内、上から2つは確実に求められるかと思います。
業務に使用するパソコンに関しては、8GB以上、3年以内のもの推奨、CPUはi5以上・・など、細かい条件が設定されていることがあります。通信環境は光回線であれば問題ないです。
在宅では、コミュニケーションツールがパソコンオンリーなので、古いパソコンやポケットWi-Fiなどで通信環境に不安定な要因があると、オンライン会議等、業務に支障をきたすため、自分自身で、快適に仕事ができる環境を準備する必要があります。
私の場合、パソコンについては、プライベートと業務併用はこわいので、思いきって中古パソコンを購入しました。中古といえど、求められるパソコンは高スペックなので、けっこうな負担額です。
在宅ワークの業務委託では、初期コストがかかる可能性がある点、注意が必要です。
簡単に業務委託契約解除はできない
「辞めたいけど言い出しにくい」「簡単に退職させてもらえない」「会社の人と顔を合わせず退職したい」・・など。
そんな風にどうしようもなく退職したい時、最後の砦として、自分に代わって会社と退職の交渉をしてくれる、退職代行サービスがあります。
一般企業、弁護士、労働組合法人など、事業を行っている団体は様々です。
労働法で守られているパート、アルバイト、契約社員、派遣社員の立場であれば、一般的に2万円前後~退職代行を依頼することができます。
しかし、筆者が退職代行10社以上を調査したところ、業務委託契約に対する対応は、下記いずれかになりそうです。
- 業務委託は対象外
- 契約解除をすることは可能だが損害賠償請求対応不可 万全を期すなら弁護士紹介
- 弁護士の業務委託退職向けサービスでは対応可能(価格相場6万円前後~)
業務委託は労働法で守られていないので「契約内容」がすべてである点がネックです。
業務委託契約書で定められている「業務遂行」「契約解除」「損害賠償」などの項目において、いずれかの契約不履行が生じた場合は、損害賠償請求される可能性が高いため、契約解除は簡単にはできないのです。
どうしても今すぐ辞めたい場合は、お金がかかっても弁護士の専用サービスを利用して退職しましょう。

私が、とある退職代行会社に相談したところ、業務委託の契約不履行の場合は、多額の損害賠償請求になるパターンが多いので、それに比べたら6万円程度の弁護士費用ですむのは安いと思っていただけるはずと言われました。
契約の拘束力が強く、基本的には理由なき自己都合での退職は許されません。
特に請負契約の場合は、業務に対して成果物を完成させる責任を負っているため、完成させないで途中でやめる=損害賠償請求される可能性大ですので、注意が必要です。
- 【基本】契約書を細部まで読み、責任を全うしたタイミングで、契約解除のルールに従い、申し出を行う(特に業務請負契約の場合は注意)
- どうしても途中で辞めたいときは、弁護士の退職代行サービス(6万円前後~)を利用する【弁護士でも対象外の場合があるため、業務委託対象か確認する】
まとめ:リスクを知った上で開業を!
以上、業務委託で働く6つの注意点を紹介しました。
- 業務委託は労働法で守ってもらえない 自分のことは自分で守るしかない
- 個人事業主として開業は必要なのか? 事業か非事業かの判断は素人には難しい!契約内容によっては不要な場合もあるため要確認
- 開業すると夫の社会保険扶養を抜けなければならない可能性がある(家族手当対象外にも注意) 業務委託締結前に夫の勤務先に確認すると安心。扶養に入れるのであれば開業して青色申告がオススメ
- 最低賃金法で守られないため働き損に注意 時給で働けない契約の場合は要注意
- 仕事で使うものは自分で準備が必要になる場合がある 初期コストがかかる可能性あり
- 簡単に業務委託契約解除はできない 契約不履行の場合は損害賠償請求されるため注意(どうしても今すぐやめたい場合は弁護士の業務委託専用サービスに相談を)
扶養から抜けたとしても収入アップの見込みがある場合や、夫の会社が個人事業主でも扶養に入れる場合は、開業し、事業所得として青色申告が一番お得になるかと思います。
そのような状況でない場合、業務委託という雇用形態でなくても、完全在宅で募集している求人はありますので、確実に夫の扶養の範囲内で働きたいなら、労働法で守られているパート・アルバイト・契約社員・派遣社員など、安心安全な雇用形態から選ぶことをオススメします。
夫の扶養の範囲内で働きたいのに、業務委託という働き方を選択したばかりに、働き損をすることがないよう、軽い気持ちでの開業にはくれぐれもご注意ください。
